プロが徹底解説!アスベスト含有調査の義務化と実務トラブル回避法

2025年4月から、建築物のアスベスト(石綿)含有調査に関する法的義務がさらに強化されました。これにより、解体や一定規模以上の改修を行う全ての工事で、事前調査結果の国への報告が必要になり、調査そのものも有資格者による実施が求められるようになっています。
とくに法人が発注者となる改修・補修工事では、報告義務を怠った場合の行政処分、現場停止、工期遅延といった実務リスクが現実的なものとなっており、元請・発注者としての責任は年々重くなっています。
今回のお役立ちコラムでは「アスベスト含有調査の義務化と実務トラブル回避法」について解説します。
2025年義務化で何が変わったか?アスベスト含有調査の最新制度概要
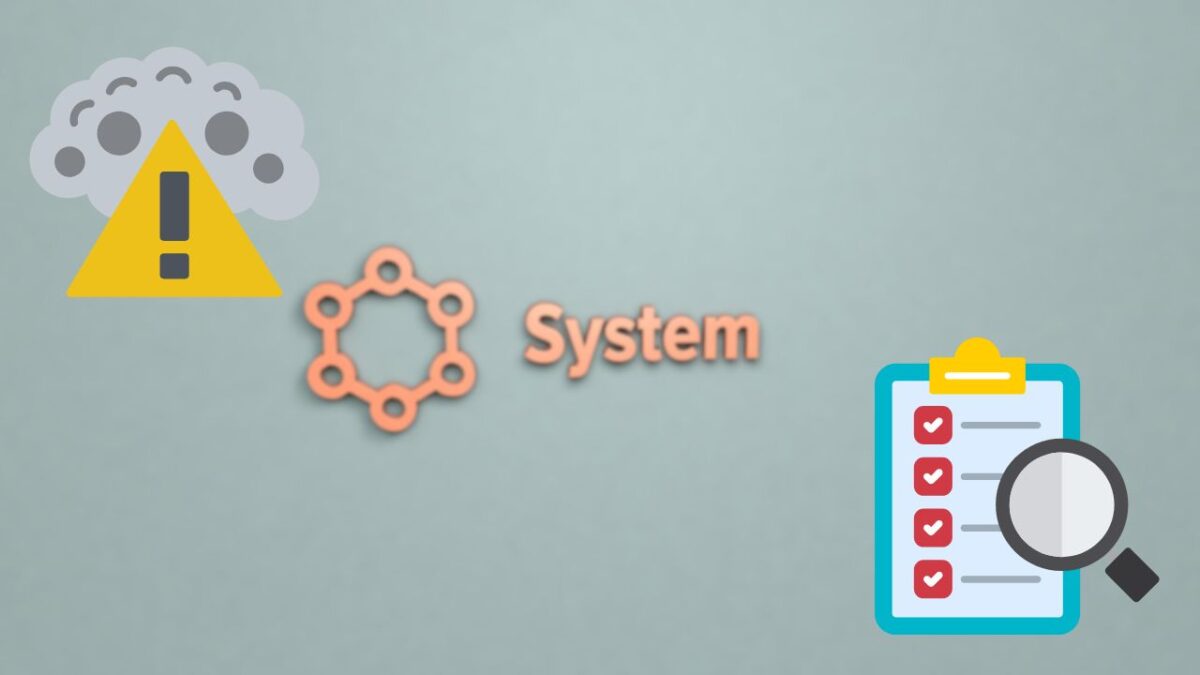
建築物に使用されたアスベストを巡っては、長年にわたり健康被害や環境問題が社会課題として取り上げられてきました。2025年4月の制度改正では、石綿含有建材の事前調査および報告体制に抜本的な見直しが加えられ、企業側にはこれまで以上の法令順守と実務対応が求められています。
法改正の背景と2025年義務化の内容
今回の義務化は、アスベスト飛散による健康被害を未然に防ぐとともに、現場でのずさんな調査や形式的な報告を防止することを目的としています。2025年4月以降は、建築物の解体および一定規模以上の改修工事において、着工前にアスベストの含有調査を行い、国(電子システム経由)への事前報告が義務化されました。
対象となるのは、昭和31年(1956年)から平成18年(2006年)までに建設された建築物で、外壁材・天井材・床材などの仕上げ層や下地にアスベストが使用された可能性があるものが該当します。
また、調査を実施できるのは「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者に限られ、無資格者による調査は法令違反となります。これにより、現場調査・報告書作成・行政対応までを包括的に担える専門業者の選定が重要な課題となってきました。
加えて、厚生労働省と環境省は制度の実効性確保のため、違反事例の公表や立ち入り検査を強化しています。形式的な対応では通用しない時代に入ったことを、法人発注者として明確に認識する必要があります。
報告義務の対象工事と報告先・提出期限の明確化
2025年4月以降、アスベストに関する報告義務が強化されたことで、従来は任意とされていた範囲の工事も含めて、事前調査結果の提出が法的義務となりました。法人としての施工・発注においては、どの工事が対象となるのか、どのような手続きが必要なのかを正しく把握しておく必要があります。
まず報告が義務付けられるのは、以下の3種の工事です。
- 建築物の解体工事(床面積合計80㎡以上)
- 建築物の改修工事(アスベストを含む建材を使用している可能性があるもの)
- 工作物に係る解体・改修工事(煙突、ボイラーなど含む)
これらに該当する工事を行う場合、着工の14日前までに「石綿事前調査結果報告書」を電子システムで提出しなければなりません。この電子報告は、厚生労働省の「石綿事前調査結果報告システム」上で行われ、原則としてオンライン完結が求められます。
提出対象となるのは、元請事業者(または直接施工する法人)であり、下請けに任せた調査結果であっても、報告義務は上位の元請側に残ります。提出が遅れた場合、着工そのものが認められないだけでなく、報告漏れによって労働基準監督署・都道府県担当部局からの是正指導・指名停止・罰則通知を受けるリスクがあります。
報告様式には「調査者の資格証明」「対象建材の種類と部位」「採取分析の有無」「写真資料」など、詳細な情報が求められます。これらを正確にまとめるには、現場調査だけでなく事前設計や過去図面との整合性の確認も必要で、調査業務を熟知したパートナーの存在が欠かせません。
また、電子報告を補助する民間ツールや委託代行サービスも増加傾向にありますが、最終的な法的責任は発注者または元請が負うため、形式に頼らず内容を正しく把握し、提出のタイミング管理まで含めた体制構築が不可欠です。
無資格者調査の罰則と義務調査者の要件
アスベスト含有調査の法改正に伴い、2023年から段階的に導入されていた「有資格者による調査義務」が、2025年4月の制度完全施行により全国で本格的に運用されています。これにより、無資格者による調査結果は一切認められず、報告を行ったとしても法的に無効とされる点に注意が必要です。
具体的には、建築物のアスベスト調査を行うためには、以下のいずれかの資格を保有していることが義務づけられています。
- 建築物石綿含有建材調査者(厚生労働省告示第70号)
- 一般建築物石綿含有建材調査者(簡易な用途向け)
- 特定建築物石綿含有建材調査者(大規模・複雑構造向け)
調査者には、アスベストに関する専門知識と建築構造の理解の両方が求められ、資格取得後も定期的な更新講習や実務経験が必要です。無資格の作業員が現場で調査を行った場合、たとえ内容に問題がなくても「無資格による調査」として行政報告が受理されず、改めて資格者による再調査が必要になるケースが多発しています。
このような事態が発覚した場合、都道府県または労働基準監督署は、元請会社・発注者に対して是正勧告、指導票の発行、場合によっては刑事告発を含む行政処分を実施します。特に公共工事や元請が大手ゼネコンである場合、信用毀損や指名停止処分が実務的なリスクとして現実化します。
法人発注者にとって重要なのは「調査会社に依頼しているから安心」ではなく、その会社が適格な資格者を配置しているか、報告体制が整備されているかを契約段階で明示的に確認することです。契約書・見積書内に「調査者資格名・登録番号・報告者名」を明記することは、トラブル防止の観点からも不可欠です。
有資格者による現場同行調査→報告書作成→報告代行までワンストップ対応できる業者であれば、発注側としての管理負担を大きく軽減でき、制度遵守と工期順守の両立が実現しやすくなります。
実務で起きやすいアスベスト調査トラブルとその対策

アスベスト含有調査の義務化が制度として明確になったとはいえ、現場の実務においては想定外のトラブルや、調査体制の不備による遅延・行政指導が後を絶ちません。発注者や元請企業にとっては、単に調査を委託すれば済むという問題ではなく、工程全体を俯瞰しながら、調査・報告・設計・施工の連携をシステムとして構築する必要があります。
設計変更・現場変更時の「調査漏れ」リスク
設計変更や施工対象範囲の追加は、建築現場では日常的に発生します。しかし、アスベスト調査の義務は当初の設計図面だけでなく、変更後の実施工範囲に対しても適用されることが原則です。実際には、変更内容が軽微であると誤認した結果「その部分だけ調査されていなかった」というケースが問題視されることが増えています。
とりわけ外壁リフォームや屋根の張り替えにおいては「補修範囲の追加」や「破損箇所の拡大」により、初期調査に含まれていなかった建材が新たに露出する場合があります。この際に再調査を怠ると、報告書の不備として行政から是正指導を受け、着工の差し止めや報告やり直しが発生するリスクがあります。
発注者・元請企業としては、工事変更時にアスベスト再調査が必要となる可能性を契約書・発注仕様書に明記し、変更時の再調査フローをあらかじめルール化しておくことが、リスク回避につながります。
サンプル採取・分析結果の信頼性と調査会社の選定基準
調査そのものは形式的に完了していても、肝心のサンプル採取や分析方法に問題がある場合、報告内容が無効とされるリスクがあります。とくに、価格競争のみを重視して選定された調査会社によっては、分析機関が非公認だったり、採取手順がJIS規格に適合していなかったりといったケースが現場で確認されています。
厚生労働省は、アスベスト分析において「JIS A 1481-1〜3」などの基準を厳格に定めており、これに準拠しない分析結果は認められません。また、検体数が適正でない場合や、採取位置が曖昧なまま報告書に記載された場合、後日現地確認で不整合が生じることもあります。
こうしたリスクを避けるには、調査実績の豊富さと行政対応力のある事業者を選定することが重要です。たとえば石井建装では、有資格者が現地調査に同行し、採取・撮影・分析委託先の選定・報告書作成までを自社で統括。行政指導や追加提出が生じた場合にもスピーディに対応可能な体制を構築しています。
届出遅延・様式不備による工期遅延とその損失
アスベスト調査に関する報告義務は「工事の着工14日前提出」が原則とされており、遅延した場合には着工が認められず、予定工程の全体がずれ込むリスクがあります。特に下請け企業や現場代理人に報告対応を任せきりにしていると、報告様式の不備や提出漏れが発生しやすくなります。
実際の現場では、次のようなトラブルが多く発生しています。
- 調査は完了していたが「石綿事前調査結果報告システム」への登録を失念
- 書類は提出したが、添付ファイル(写真・図面)の形式が不適合で差し戻された
- 調査対象が変更になったにもかかわらず、再報告を行わなかった
これにより、元請企業が賠償責任を問われ、顧客からの信頼を損なう結果となるケースも報告されています。
回避策としては、社内でのWチェック体制を構築し、報告提出スケジュールを工程表に組み込むとともに、調査会社側に「提出代行対応の有無」を確認することが求められます。石井建装のようなワンストップ体制を持つ企業であれば、報告書完成から提出、確認完了までを確実にフォロー可能で、元請の負担軽減にも直結します。
アスベスト調査の実務対応を委託する際のチェックポイント
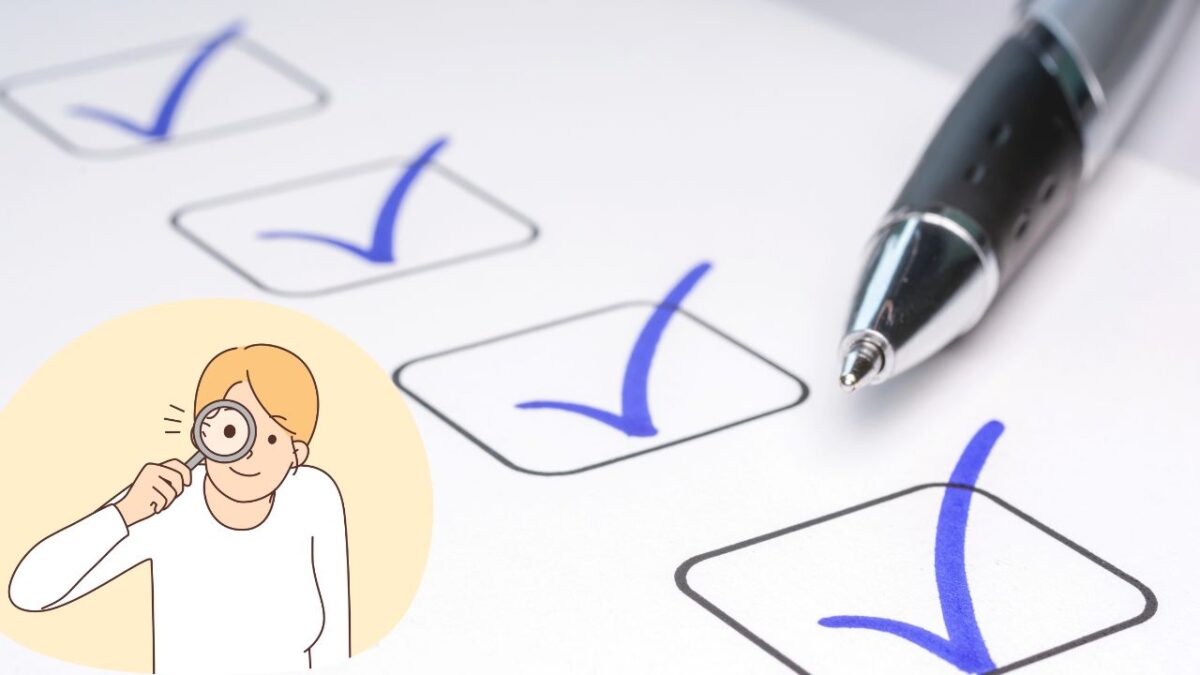
アスベスト含有調査は単なる現場作業ではなく、報告制度の厳格化に伴い、契約管理・提出物管理・行政手続きまでを含めた高度な運用が必要な業務となっています。
特に法人発注者・元請企業は、調査業務を外部に委託する場合、その選定基準や契約内容の整備を怠ると、結果的に法令違反や工期遅延の責任を問われるリスクを負うことになります。
見積段階で確認すべき必須項目と契約時の注意点
アスベスト調査業務を外注する際には、調査会社の提案書や見積書において、単に「調査一式」「報告書作成含む」といった曖昧な記載があるだけでは不十分です。報告制度上必要となる情報と実際の業務内容をすり合わせる形で、契約前に以下の点を明示的に確認しておく必要があります。
- 対象建材・部位・数量の明確化(外壁材・軒天・下地材など)
- 分析方法(JIS A 1481準拠)・検体数・分析機関名の明記
- 報告書構成・提出媒体(PDF/紙/電子システム対応)
- 調査者資格の記載(氏名・資格証番号)と立ち会い有無
- 行政提出の代行可否と、その追加費用の有無
これらが見積段階で明記されていない場合、後工程で追加請求が発生し、報告不備が発覚する可能性が高くなります。また、契約書や発注書においても、再調査時の対応条件・費用負担区分・キャンセル時の処理ルールなどを盛り込むことが重要です。
調査報告書の品質確認ポイントと保存義務
アスベスト調査においては、報告書の体裁・内容の整合性がそのまま行政提出資料となるため、報告書の品質は施工品質と同等以上に厳しく管理すべき対象です。見逃されがちですが、調査完了後の書類チェックを行わないまま行政報告を済ませてしまい、後日不備で差し戻されるという例も少なくありません。
良質な報告書には以下の要素が網羅されています。
- 建物全体の位置図・立面図と採取部位の照合資料
- 各部位ごとの含有有無の判定表(分析証明書添付)
- 分析手法と検査機関の登録証明
- 現場写真、採取日時、調査担当者の記録
また、報告書は3年間の保存義務があり、紙保存だけでなく電子ファイルでのバックアップを整備しておくことで、将来の行政調査・再提出にも対応可能です。社内文書管理体制の一部として、ファイル名・保管場所の標準化もあわせて推進することが望まれます。
補助金・助成金の活用と対象工事の整理
近年、老朽建築物のアスベスト対策を推進する目的で、自治体単位で調査・分析費用の一部を助成する制度が整備されつつあります。中小企業や中堅工場にとっては、補助制度を活用することで、法令対応とコスト削減を同時に実現できる可能性があります。
たとえば、茨城県内でも過去に以下のような制度が実施されています。
- 茨城県建築物アスベスト調査補助金(例年:予算制・先着順)
→ 調査費用の1/2(上限20万円)を補助 - 取手市内の工場・事業所対象リフォーム支援(防災・環境対策として認定)
→ アスベスト調査+外壁改修を対象に一部助成(制度変更あり)
なお、制度は年度ごとに要件や申請期間が変動するため、施工予定の前年度秋頃〜年度初頭にかけて制度確認を行い、計画段階から補助金申請を想定することが重要です。
行政制度の運用実績を持つ施工会社であれば、必要書類の準備や申請書作成支援まで一括で対応可能です。
法令順守と工期遵守を両立するアスベスト対応の最適解
アスベスト含有建材の調査と報告義務は、2025年の法改正により形式的な処理では済まされない領域へと進化しています。元請企業や法人発注者には、単なる義務対応にとどまらず、工期・予算・安全性を総合的にコントロールするマネジメント体制の構築が求められます。
トラブルの多くは、制度の理解不足や調査範囲の誤認、報告業務の属人化によって発生しており、結果として着工遅延や行政指導、信頼損失といった重大な影響をもたらします。
これを防ぐには、次の3点が実務上の鍵となります。
- 有資格者による正確な現地調査と報告体制
- 契約・仕様段階からの明確な調査範囲と対応項目の明記
- 提出期限と行政手続きに対するスケジュール管理の徹底
こうした要件を満たすためには、単に安価な業者を選ぶのではなく、制度対応実績を持ち、行政連携・補助金対応にも精通した施工パートナーの選定が不可欠です。
アスベスト調査・行政報告でお悩みなら石井建装へ|制度対応から助成金活用までトータルサポート

2025年の法改正でアスベスト含有調査・行政報告のハードルが大きく上がり、「自社で本当に対応できるか不安」「調査会社選びで失敗したくない」という声が増えています。
プロタイムズ取手店・プロタイムズ我孫子店・プロタイムズつくば学園店/株式会社石井建装では、有資格者が現地同行し、設計・現場変更まで対応した事前調査から、電子報告書の作成・行政提出、補助金申請サポートまでワンストップでお手伝い可能です。
契約時の調査範囲明記や報告書の品質チェック、行政提出のスケジュール管理も徹底し、法人発注者や元請企業様のリスクと負担を最小化。書類不備や届出遅延による工期遅れ・行政指導も、社内Wチェック体制と豊富な現場経験で回避できます。
「調査会社の資格や分析体制が分からない」
「報告システムの運用で困っている」
「補助金や助成金もフル活用したい」
とお考えの方は、ぜひ一度石井建装にご相談ください。
問い合わせフォーム、メール、電話はもちろん、ショールームでのご相談も歓迎。
石井建装がトラブル回避と安全・確実なアスベスト対応を力強くサポートします。
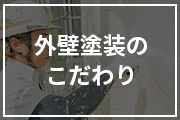
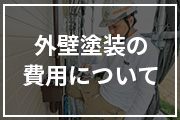
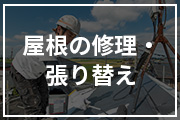
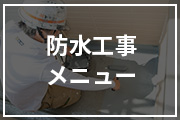

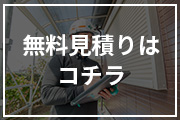

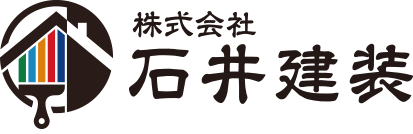
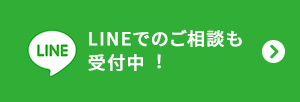











コメント