ベランダ防水“10年で要交換?”は本当か|劣化診断の正しい基準
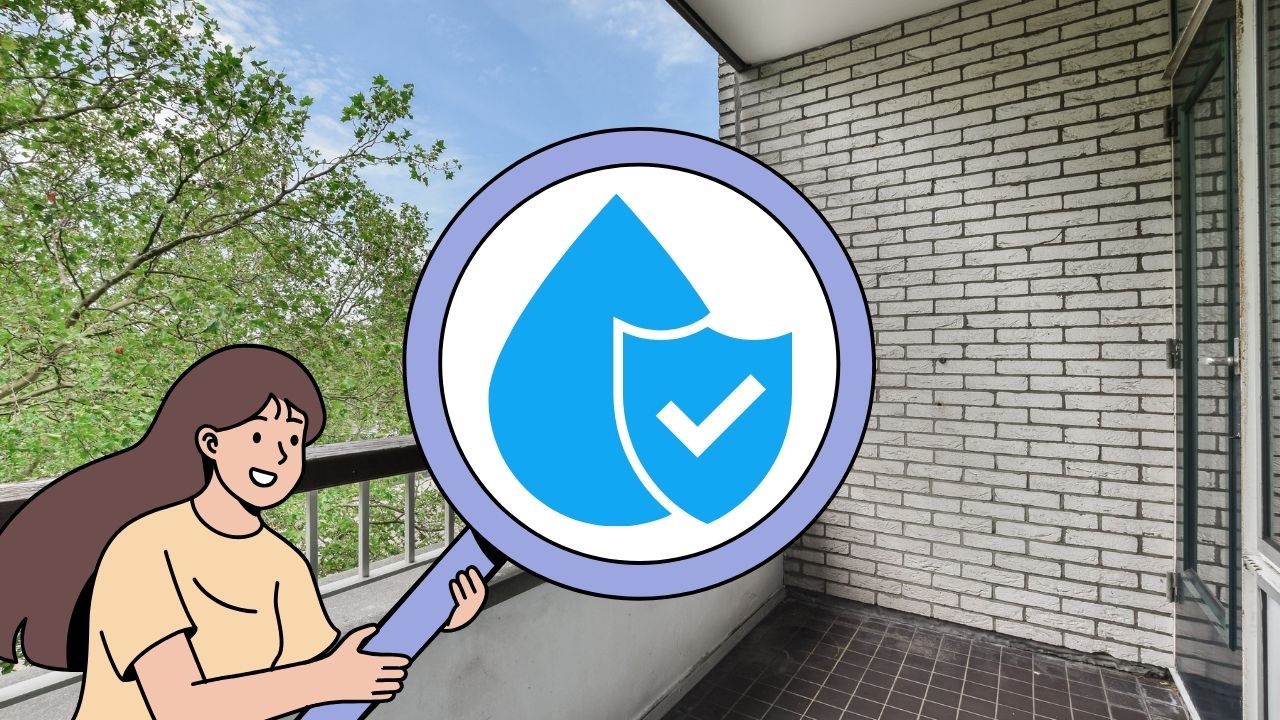
ベランダ防水は「10年経ったら交換」といわれることもあります。しかし、10年という数字だけで交換を決めるのは早計です。防水層の劣化は、施工方法・立地環境・日照・排水状態などによって大きく異なり、年数よりも「状態を見極めること」が大切だからです。
今回のお役立ちブログでは、劣化症状別の判定チャートを用いながら、交換が必要なケースと不要なケースを明確にし、正しい診断基準をお話しします。
10年という数字の根拠とは?メーカー保証と耐用年数の違い

ベランダの防水性能は10年といわれても、それより短くなるケースもあります。寿命や保証期間について、見てみましょう。
ウレタン・FRP・シートで異なる「寿命」
「10年で交換」といわれる背景には、防水材ごとの設計上の耐用年数があります。ウレタン防水は10〜12年、硬質なFRP防水は10〜15年、耐久性に優れるシート防水は12〜20年とされています。
ただし、あくまで環境条件を一定に保った場合の理論値です。紫外線が強いベランダや排水が悪い立地では、5〜7年で劣化する場合もありますし、定期的にトップコートを塗れば20年以上維持されるケースもあります。長持ちさせるには、劣化に応じたメンテナンス・補修が必須です。
「保証期間=交換タイミング」ではない理由
防水工事には、施工店やメーカーによる保証期間(5〜10年)が設けられています。しかし「施工上の不備があった場合に無償で対応する」というものであり、性能が10年で切れるわけではありません。
たとえば、保証期間中に定期点検やトップコートの再塗りを行うと、防水層の延命につながります。
年数よりも“劣化症状”で判断することが大切!数字に踊らされてはいけない理由とは?
10年という目安は、あくまで“点検のタイミング”です。交換の必要性は症状の有無で判断します。10年経っても交換不要なケースと10年以内でも交換した方が良いケースについて、見てみましょう。
10年経っても交換不要なケース
10年経っても交換不要な可能性が高いケースは次の通りです。
- 防水層に光沢が残り、色あせや白化が軽度
- ひび割れや膨れがなく、指で押しても弾力がある
- 排水口まわりにカビや浮きがない
- 雨の後も水たまりができず、乾きが早い
これらの状態であれば、防水層は健全と判断できます。トップコートの再塗りだけで延命が可能です。近年では、紫外線反射性トップコートやフッ素系トップコートも登場しています。
10年以内でも交換した方が良いケース
次のような症状がある場合は、5~8年しか経過していなくても交換を検討した方が良いかもしれません。
- 表面のひび割れや膨れが広範囲にある
- 塗膜が剥がれ、下地のガラスマットやコンクリートが見える
- ベランダ下の天井に雨染みや黒カビがある
- 地面を踏むと「ブヨブヨ」と沈む感触がある
内部に水分が浸入しているサインで、部分補修では追いつかない場合が多いでしょう。放置すると木下地の腐食や雨漏りに発展するため、下地からのやり替えが必要です。中でも「踏むと柔らかい」「黒ずみが取れない」場合は、すでに合板が水を吸って膨張している可能性があります。
ベランダ防水工事の内容は劣化症状で異なる!対応方法の違いとは?

実際の判断を簡単に行えるよう、下記のセルフチェック表を活用しましょう。症状・状態・対応は次の通りです。
| 症状 | 状態 | 対応 |
| 色あせ・軽いひび | 軽度劣化 | トップコート再塗り |
| ひび割れ・膨れ | 中度劣化 | 部分補修+再塗り |
| 防水層の剥離・下地露出 | 重度劣化 | 全面やり替え |
| 雨染み・漏水 | 深刻 | 下地修復+防水再施工 |
軽度の劣化なら補修で対応可能
軽度の劣化であれば、補修で対応可能です。しかし、表面の変色や小さな膨れがある場合は、内部に水分が溜まっているケースもあります。よって、細かく調査してもらうことが大切です。
診断は「目視+測定」で行うのが理想
専門業者は、次のような計測機器を用いて客観的なデータを取得します。
- 含水率計:防水層や下地内部の湿度を数値化し、水の侵入を確認
- 赤外線カメラ:漏水箇所や断熱欠損部を可視化
- ベランダ防水工事が必要な劣化症状と修理方法
専門業者にデータをもとに現状を判断してもらえば「表面は綺麗でも内部が劣化している」といったトラブルを見逃さずに済みます。とくに、梅雨明けや台風シーズン直後は含水率が一時的に高まる傾向があるため、測定時期も重要です。
ベランダ防水の交換を行う際はポイントがある!何が大事?
ベランダ防水の交換を行う際のポイントを見てみましょう。
トップコート再塗りで寿命を延ばす
ベランダ防水の劣化は、紫外線によるトップコートの硬化が主な原因です。防水層が傷んでいないうちに再塗りを行えば内部層を保護するため、寿命を延ばせます。
また、近年は低臭タイプのトップコートや速乾性樹脂も普及しており、1日で仕上がるケースもあります。共働き家庭やマンションのベランダなど、短工期を求める環境にもおすすめです。
再塗り時の下地処理と点検が重要
再塗り時は、既存トップコートの汚れ・油膜をケレン(研磨)で除去してから塗布することがポイントです。下地処理を省くと密着不良を起こすため、見積時に「下地調整費」が含まれているか確認しましょう。
さらに、再塗りと同時にドレン(排水口)まわりの清掃・補修も行うと安心です。排水詰まりやシーリング切れを放置すると、せっかく再塗りをしても浸水リスクが残ります。中でも角部やサッシ下は局所的に水が溜まりやすいため、点検しましょう。
業者にベランダ防水工事を勧められた場合は慎重になることが大切!業者選びのコツとは?

業者に防水工事を勧められたものの、依頼して良いか迷うケースもあると思います。業者選びでは、次のことを意識すると良いでしょう。
見積書の中身を確認する
見積書では、次の項目を確認しましょう。
- 防水の種類(ウレタン・FRP・シート)
- 施工範囲(㎡数)
- 保証年数と範囲
- トップコート塗布の有無
- 下地補修費の有無
これらが曖昧な見積書は、追加請求リスクが高いといえます。「既存防水撤去費」や「勾配調整費」は後から発生しやすいため要注意です。
提案を鵜呑みにせず複数の業者から話を聞く
同じ条件で複数社に見積りを取って、写真と測定値で根拠を示してくれる業者に任せましょう。見積書に「膜厚測定結果」や「含水率データ」を添付する業者は、診断力と説明力の高い証拠です。
一方「表面を見ただけで即交換を提案する業者」は、警戒した方が良いでしょう。
【FAQ】ベランダ防水交換に関してのよくある質問
ベランダ防水の交換に関する「よくある質問」をQ&A形式でお話しします。
Q.ベランダ防水は自分で点検できますか?
A.表面の色あせやひび割れは確認可能です。しかし、内部の含水や浮きは専門機器でしか判断できません。専門業者の点検をおすすめします。
Q.トップコートだけ塗れば防水効果は戻りますか?
A.軽度劣化なら有効です。防水層まで痛んでいる場合は一時的な延命にとどまります。弾力が失われていたら、再施工が必要です。
Q.FRPとウレタン、どちらが長持ちしますか?
A.FRPは硬く耐摩耗性に優れていますが、下地の動きに弱い点があります。ウレタンは柔軟で密着性が高く、木造住宅には適しています。建物構造と動きに合わせて選びましょう。
防水層の寿命を見極めるなら“状態診断”がカギ|石井建装の無料点検で安心リフォームを

「10年経ったら防水を交換」と聞くことがありますが、実際には年数よりも“現状の状態”が判断基準です。紫外線や排水状況、施工精度によって劣化スピードは大きく異なり、まだ再塗りで延命できるケースもあれば、5年で交換が必要な場合もあります。表面のひび割れやブヨつきは、内部に水分が侵入しているサイン。放置すると下地腐食や雨漏りにつながるため、早期の点検が欠かせません。
石井建装では、含水率計や赤外線カメラを用いた精密診断により、目視だけでは分からない内部劣化を可視化します。防水工事が本当に必要か、トップコートの再塗りで対応できるかを的確に判断し、過剰な工事を防ぐことが可能です。ベランダ防水の状態に少しでも不安を感じたら、石井建装までお気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム、メール、電話、ショールームでのご来店もお待ちしております。
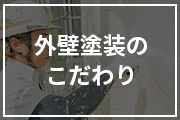
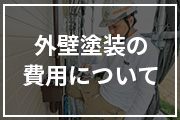
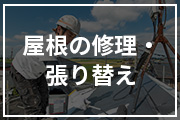
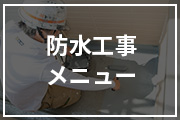

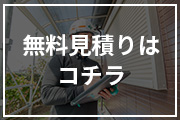

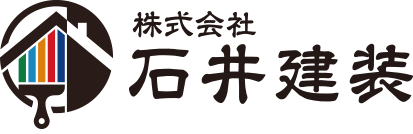











コメント