見積で“m数”が違うのはなぜ?|シーリング・板金・足場の計算式と許容差
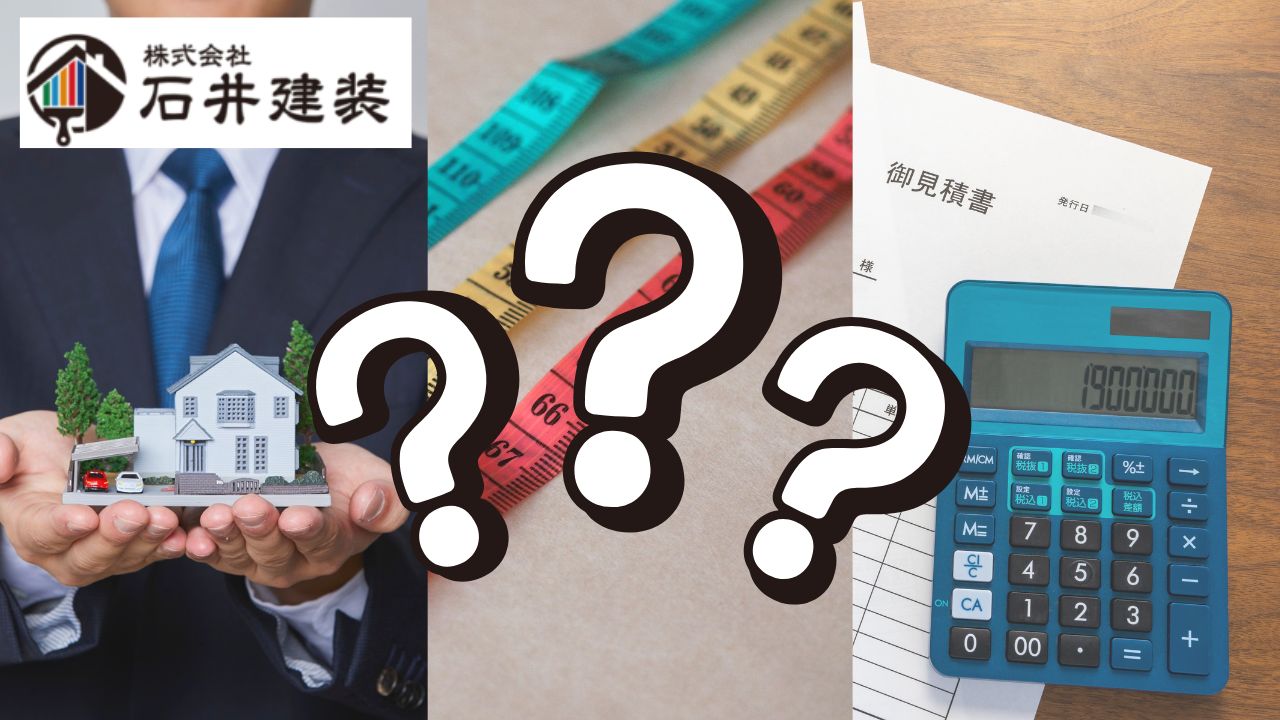
💬「えっ、同じ家を塗装してもらうのに、業者によって見積の“m数”が全然違う…!」
こんな経験、ありませんか?シーリング・板金・足場など、外装工事では「㎡(平方メートル)」だけでなく「m(メートル)」単位での算出項目が多く、このm数の違いが見積金額の差を生む最大の要因となります。
今回のお役立ちコラムでは、外装リフォーム業界のプロが見ているm数の計算根拠と許容差の目安を、実際の図面や現場事例をもとにわかりやすくお話していきます。「なぜ安いのか?」「どこまでが正しいのか?」を見極めるためのチェックポイントを整理します。
m(メートル)とは? ― 見積の基本単位を理解しよう
まず押さえておきたいのは、「m(メートル)」という単位が何を指すのかということです。㎡(平方メートル)は“面積”ですが、mは長さの合計を表します。外壁や屋根の見積では、この違いを理解していないと“数字のマジック”に惑わされがちです。
小学校でも習ったワードだと思いますが、施工として見たときに何を表す言葉になるのか、今一度整理しておきましょう。
- ㎡(平方メートル):塗装などの「面」を扱う単位。外壁や屋根など、塗布面積を示す。
- m(メートル):長さを扱う単位。シーリング目地や板金、足場など「線・辺・周囲」を計算する際に使用。
たとえば、30坪(外壁約150㎡)の住宅でも、シーリング目地の総延長は250〜350mになることがあります。つまり、㎡単価が同じでもm数が違えば金額は大きく変わるのです。
なぜm数が違う? ― 「測り方」と「拾い方」で差が出る

同じ家なのに業者ごとにm数が違う理由は、「測り方のルール」と「拾い方(算出範囲)」に違いがあるためです。ここでは、代表的な3つの項目――シーリング・板金・足場について、それぞれの計算基準を見ていきましょう。
シーリング(コーキング)のm数が違う理由
シーリングはm単位で見積される代表的項目です。しかし、実際には「どの目地を含めているか」「両側打ちか片側か」で数値が大きく変わります。
計算式の基本を把握しておきましょう。
シーリングの見積は【各目地の長さ × 本数】=合計m数で算出します。
たとえば、外壁1面に縦目地5本(3m)+横目地2本(8m)がある場合:
(3×5)+(8×2)=31m。これを4面分で約120〜140m。
実際の現場ではこれに「サッシ周り」「入隅」「庇周り」などを加算し、全体で250〜350mになるケースが多いです。
▶差が出るポイント
| 要素 | 拾い方の違い | 差の理由 |
| サッシ周り | 含める/含めない | 数十m単位で変動 |
| 目地幅 | 9mm/12mmなど | 打設量が2割以上変わる |
| 増し打ち/打替え | 片側か両側か | 施工量が倍近く変動 |
| バルコニー内側 | 省略されやすい | 隠れ目地を見落としがち |
▶注意点
「うちは200mでした」「他社は300mでした」と聞いたとき、どちらが正しいかはどの部位を拾ったかで決まります。m数が少なすぎる場合は「そもそも省略されている可能性」を疑いましょう。
板金のm数が違う理由
屋根や外壁の板金(棟板金・水切り・笠木など)もm単位で計算される項目です。ただし、曲がり部分・ジョイント部・重ね代の扱い方で差が出やすいのが特徴です。
板金の場合の計算式の基本を把握しておきましょう。
板金工事では、【実寸の長さ+重ね代+ジョイント分】=合計m数で算出します。
たとえば棟板金が10mある場合でも、ジョイントや重ね代を含めると 12〜13m になるのが一般的です。
▶差が出るポイント
| 要素 | 拾い方の違い | 差の理由 |
| 重ね代 | 含めるかどうか | 10〜15%の差が出る |
| コーナー部 | 別途計上する/含める | 加工費が発生 |
| 材料長さ | 3m定尺/4m定尺 | 端材ロス分を含むか |
| シーリング込み | 含む/別途 | m単価が変動 |
▶許容差の目安
板金は構造上、多少の誤差が生じるため、±10%程度のm数差は許容範囲です。しかし、20%以上差がある場合は、拾い漏れか過小算出の可能性があります。
足場のm数が違う理由
足場費は工事全体の中でも金額差が大きく出やすい項目です。m数(正確には「㎡」ですが、外周×高さで算出されるため実質“線的”な要素)が異なると数万円単位で変わります。
足場の計算式の基本も重要ですよ。
足場の見積では、【建物外周 × 高さ】+(出隅・庇分)=合計㎡(またはm数換算)で算出します。
例)外周40m × 高さ6m = 240㎡(約240m換算)
庇・出隅・ガレージ側などを加えると、最終的に250〜300㎡程度になります。
▶差が出るポイント
| 要素 | 拾い方の違い | 差の理由 |
| 出隅・入隅 | 含めるか | 5〜10㎡分差が出る |
| 庇や下屋根部 | 含めるか | 上部作業分で追加 |
| 隣地との距離 | 支柱・控え足の追加 | 狭小地で費用上昇 |
| メッシュ養生 | 含む/別途 | 条件で単価変動 |
▶許容差の目安
足場計算の誤差は±5〜10%が通常となります。ただし、あまりに低い見積の場合は「安全基準未満の簡易足場」や「範囲を限定している」可能性があるため注意が必要です。
“安さの裏”を見抜く! 計算根拠の早見表

m数の違いは単なる「測り方の癖」ではなく、“安く見せる”ための意図的な省略であることも少なくありません。ここでは、よくある「数字のトリック」を早見表で整理します。
| 項目 | 表面的に安く見える手法 | 実際のリスク |
| シーリング | サッシ周り・入隅を除外 | 雨漏り再発・剥離の原因 |
| 板金 | 重ね代を除外 | 雨水逆流・腐食リスク |
| 足場 | 出隅・庇を除外 | 高所作業の安全性低下 |
| 塗装 | 下地処理を㎡に含めず | 膜厚不足・早期劣化 |
| 防水 | 下地補修を別途扱い | 想定外の追加費用 |
「安い=悪い」とは限りませんが、“どこまで含まれているか”を明文化している業者ほど信頼できるのは事実です。数字よりも、計算の根拠があるかどうかをチェックしましょう。
許容差の目安と判断基準
では、実際にm数が違っていた場合、どこまでが許容範囲なのでしょうか?ここでは、一般的な工事別の“誤差許容ライン”をまとめます。
| 工事項目 | 許容差の目安 | チェックポイント |
| シーリング | ±10〜15% | 拾い方(サッシ・入隅)を確認 |
| 板金 | ±10% | 重ね代・コーナーの扱い |
| 足場 | ±5〜10% | 出隅・庇・メッシュ範囲の有無 |
この範囲を超える差が出ている場合「測り方の違い」というより計算根拠が曖昧である可能性が高いです。不明点がある場合は、遠慮せず“どの部位を含めたm数か”を具体的に尋ねましょう。
事例で見るm数の違いと価格差

ここでは、茨城県内で実際に施工されている住宅塗装・防水工事の平均的な傾向をもとに、
m(メートル)数の違いがどのように見積金額へ影響するかを具体的に見ていきます。事例は、茨城県内の戸建住宅(延床30坪前後・2階建て)を想定した一般的なケースです。
地元業者が公表している施工実績や、複数社の見積データをもとに再構成したものであり、
特定の会社や個別現場に限定したものではありません。つまり、“現場で実際によく起きている差異”を再現した代表事例として捉えてください。m数の差は、「図面の読み方」「測定方法」「補修範囲の考え方」など、それぞれの会社の計上基準によって生まれるものです。
このような前提を理解した上で見積を比較すれば、単に「高い・安い」という価格の印象ではなく、“なぜ差が出ているのか”という構造的な理由を読み取ることができます。結果として、数字だけに惑わされず、根拠ある判断ができるようになります。
事例① シーリング打ち替え工事(30坪・2階建て)
業者A: 250m × 900円=225,000円
業者B: 320m × 900円=288,000円
m単価は同じでも、総延長差70mで約6万円の差が出ます。A社はサッシ周り・庇内側を省略しており、施工後に一部から再漏水が発生。結果、再施工が必要になりました。
事例② 屋根棟板金交換(延長12m)
業者A: 10mで見積(重ね代未計上)→ 65,000円
業者B: 12mで見積(ジョイント含む)→ 78,000円
実際には12m必要で、A社では部材が不足することになります。この場合、現場追加で結果的に高くついたという事例もあります。
事例③ 足場設置(外周40m/高さ6m)
業者A: 外周×高さのみ→240㎡
業者B: 庇・出隅を含め→280㎡
単価700円でも 約28,000円差となります。ただし、B社の方が作業範囲が広く、安全性も確保されていました。
FAQ|見積のm数が違うときのよくある質問
最後に、見積比較時によく寄せられる「m数」に関する疑問をまとめました。シーリング・板金・足場など、現場での計上差が最も起こりやすい項目を中心に、理解しておくと安心できるポイントをQ&A形式で整理します。
Q. 同じ建物なのに、業者によってm数が違うのはなぜですか?
A. m数の拾い方に各社の基準差があるためです。サッシ周りや出隅、重ね代の扱いなどで数値が変わります。「どの範囲を含めているのか」を説明できる業者を選びましょう。現場実測の写真が添付されていると精度が高く安心です。
Q. 図面をもとにしたm数と、現場実測のm数が違うのは問題ですか?
A. 問題ではありません。図面は理論寸法のため、実際の建物では凹凸や補修範囲の増減が生じます。ただし、差が大きい場合は「測定方法の違い」が要因かもしれません。両方を提示してくれる業者ほど透明性があります。
Q. m単価が同じなら、m数の違いは気にしなくていい?
A. いいえ。m単価が同じでも、m数が過少なら省略、過多なら過剰計上の可能性があります。内訳根拠を確認し、必要範囲が正しく反映されているかを見極めましょう。「㎡単価 × 実測値」で計算できる見積が最もフェアです。
「m数の差」は説明できるかが決め手|石井建装なら根拠つき見積で不安ゼロへ

同じ家でも見積の“m数”が違うのは、拾い方(範囲)と計算式(重ね代・入隅・サッシ周り・庇部・足場の出隅加算など)のルール差が原因です。許容差はシーリング±10〜15%、板金±10%、足場±5〜10%が目安で、これを超える場合は省略や過剰計上の可能性があるため根拠確認が不可欠です。
石井建装では、図面+現場実測+写真(入隅・サッシ・庇・棟部のマーキング入り)をセットで提示し、必要m数=【測定根拠×算定式】を可視化。ドローン・レーザー距離計でのダブルチェックや「重ね代・ジョイント・メッシュ養生の含有可否」を明記し、追加費用の発生条件も事前に共有します。
「なぜこのm数なのか」「どこまでが範囲か」を数値で説明できるかが信頼の分かれ目です。見積の透明性=施工の透明性。数字の裏側まで理解して納得の契約を進めましょう。お問い合わせはフォーム・メール・電話のほか、ショールームでの図面持ち込み相談も歓迎です。
石井建装が適正範囲と最適コストで、後悔のない外装リフォームをご提案します。
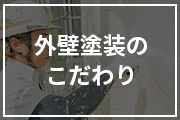
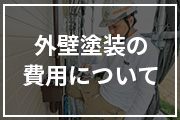
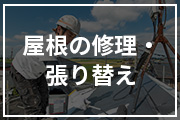
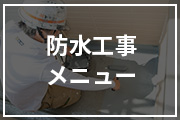

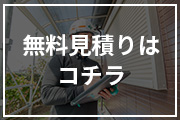

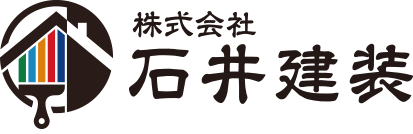











コメント