取手市|スレート屋根「カバー不可」の見分け方。野地・雨仕舞・棟板金のサイン

取手市で、築20〜25年前後のスレート屋根に「カバー工法はできますか?」という相談が増えています。屋根カバーは、既存のスレートを撤去せずに、新しく軽量な屋根材を重ねる工法です。ただし、すべての屋根に適用できるわけではありません。
表面の割れや反りだけで判断すると、あとから雨漏りが再発したり、施工後数年で浮き・バタつきが起きたりするリスクもあるのです。本当にカバー工法が適切かどうかは、屋根の「内部の状態」まで含めて見極めが求められます。
そこで今回のお役立ちコラムでは、施主様が地上からできるセルフ診断と、現場でプロが行う判定基準を分かりやすく整理してお話しします。
カバー工法の判断を左右する「3つの警告サイン」
屋根を重ね張りできるかどうかは、表面の割れや色あせよりも「内部の健全性」が重要です。ところが、その肝心な劣化ポイントは地上から目視しづらい部位に集中しているのです。
もし次の3点に不具合が出ている場合、カバー工法では根本的な改善が望めません。施工後に雨漏りや浮きが再発する恐れもあります。
野地板の沈み(下地のたわみ)
屋根材の下で建物を支えているのが野地板です。この部分が湿気や雨水で弱くなり、踏んだときに沈むような状態だと、上に新しい屋根材を重ねても固定力が十分に出ません。わずかな沈下でも、金属屋根のビスが効かず、カバー工法後のバタつきや浮きを招く原因になります。
雨仕舞の劣化(谷・壁際・棟の水処理機能の低下)
谷板金や壁際の水切りなど、雨水を外へ逃がすための重要な部分が傷んでいるケースです。ここが腐食したり、雨水の流れが乱れたりすると、カバー工法で屋根材だけ重ねても内部に水が回り続けます。
棟板金の緩み・浮き・下地腐朽
屋根の最上部にある棟板金に、釘抜けや浮きが発生している場合は要警戒です。問題は表面の金属ではありません。その下にある貫板(木下地)が腐っている可能性も高くなります。貫板が劣化していると、新しく棟板金を取り付けても釘が保持されず、強風で再び外れたり、雨水の侵入を許してしまうのです。
屋根の劣化を示す事例と画像
以下、屋根の劣化に関する代表例を事例画像とともにお話しします。
築20年前後で表面不良が急増する理由(吸水・反り・割れ)

築20年前後で増えるスレート屋根の反り・割れの事例です。吸水と乾燥を繰り返すことで内部から劣化が進みます。スレート屋根は、施工直後こそ強度はありますが、築15年を過ぎたあたりから吸水と乾燥を繰り返し、内部の繊維が弱くなるのです。
取手市の住まいでも、屋根表面に反り・割れ・欠けが目立ち始めるのは、この時期の傾向があります。
とくに吸水したスレートは膨張→乾燥→収縮を繰り返すため、目に見えない微細なクラックが内部で進行するのです。このような現象は一般的に「経年劣化」と片付けられがちですが、問題は「内部の劣化が外側より進んでいる場合も多い」という点にあります。
表面の軽度な割れだけだとカバー工法も不可能とは言えません。ただし、内部強度が低下している屋根材にカバーを行うと、ビス保持力不足や金属屋根の浮きが短期間で発生することがあります。
取手市の気候特性(湿度・降雨・冬の冷え込み)が屋根劣化を早める仕組み
取手市周辺は、関東内でも年間湿度が高めの日もあります。梅雨から秋雨の長雨の時期では、屋根材が常に湿気を帯びやすい環境です。
スレートが吸水した状態で冬の冷え込みを迎えると、表面で凍結膨張が起きます。結果、微細な層間はく離が発生するケースもあるのです。
苔や藻の繁殖が多い屋根は、すでに吸水が進んでいるサインと言えます。苔=“湿った状態が長く続く屋根”であるため、結果として劣化速度はさらに加速するのです。
カバー工法ができない屋根の明確なライン
スレート屋根は、見た目が傷んでいてもカバーできる場合はあります。ただし、内部や下地に問題があると、どんなに丁寧に施工しても失敗します。ここがカバー不可の決定的ラインです。
野地板の沈み・踏み抜きの兆候と構造安全性

腐食した野地板です。内部に水が回っている証拠で、ビス固定が効かないためカバー工法は適用できません。
野地板とは、屋根材を支える合板のことです。カバー工法では、この野地板をそのまま利用し上から金属屋根を固定します。ただし、野地板が腐朽していたり沈み込みが生じていたりすると、ビスが効かず固定力を確保できません。
実際の調査では、屋根に乗った瞬間に「ふわっ」と沈む感覚や、歩いたときの弾力などで健全性を確認します。
野路板が柔らかいと、カバー工法をしても根本の問題は解決されません。固定不良によるバタつき・浮き・雨漏りは、高確率で再発します。野地板の腐朽は、カバー工法を不可と判断する最重要ポイントのひとつです。
雨仕舞(谷・棟・壁際)に出る「カバーでは直らない不具合」

谷板金が錆びついている事例です。雨仕舞の不具合はカバー工法では改善できません。葺き替えが必要になる代表的症状です。
屋根の雨仕舞とは、雨水が入り込みやすい谷部分・棟の継ぎ目・外壁との取り合い部などの処理を指しています。ここに不具合があると、表面のスレートを重ねても改善されません。とくに谷板金の腐食や、壁際の水切り板金の欠損は、雨の通り道そのものが破壊されている状態です。
カバー工法で金属屋根を載せても、古い雨仕舞が生きたまま内部に残ります。雨水は同じルートを通って再度内部に侵入することになるのです。「カバー工法では直らない根本的な欠陥」で、原則として葺き替えが望ましいと言えます。
棟板金の浮き・釘抜け・下地腐朽が示すカバー限界点

棟板金が劣化した状態です。内部の貫板腐朽が疑われ、カバー工法後も、不具合再発の可能性が高くなります。
棟板金の釘抜けや浮きは取手市でも見られます。問題は、釘が抜ける背景にある「内部の貫板(下地木材)の腐朽」です。貫板が濡れて腐っている場合、釘が保持されません。カバー工法で新しい棟板金を取り付けても再度浮きやすくなります。
また、貫板が湿気を含んでいる状態でカバーを行うと、内部結露や腐朽が加速しかねないのです。そうなると屋根全体の耐久性に悪影響を及ぼします。
棟板金は屋根の最上部に位置するため、劣化が進んでいる場合「屋根の内部も同じく傷んでいる」と判断される傾向です。そのためカバー工法よりも葺き替えが適切です。
FAQ|スレート屋根「カバー不可」の見分け方についてよくある質問
取手市で築20〜25年のスレート屋根を調査すると、「見た目はまだ大丈夫そうなのに、カバー工法ができないケース」が意外と多くあります。ここでは、特にご相談が多い内容を5つまとめました。
Q.取手市のスレート屋根は築何年頃からカバー不可の可能性が高まりますか?
A.築20〜25年頃から野地板の腐朽、雨仕舞の劣化、貫板の腐りが顕在化し、カバー工法不可のケースが増えます。表面の割れが軽度でも内部は大きく傷んでいることがあります。
Q.野地板が沈んでいるかどうかは、施主自身でも確認できますか?
A.安全面から屋根に上るのは避けるべきですが、地上からでも「屋根の一部が波打って見える」「棟のラインが不自然に沈んでいる」場合、野地板劣化の可能性が高いです。
Q.雨仕舞の劣化はカバー工法で改善できますか?
A.できません。谷板金・壁際水切り・棟周りの腐食や欠損は根本の水処理機能が壊れているため、表面を重ねても内部へ水が回り続けます。原則として葺き替えが必要です。
Q.棟板金が浮いている程度なら、カバー工法で直せますか?
A.表面の板金だけでなく、内部の貫板が腐っているケースが多く、釘保持力が失われています。貫板が劣化している屋根は、カバー工法後も不具合が再発するため適用不可です。
Q.カバー工法と葺き替えのどちらを選ぶべきか、自分で判断できますか?
A.不可能です。スレート内部の強度、野地板の含水、ルーフィング状態、雨仕舞の損傷などは表面から見抜けません。まずは石井建装の現地調査で可否判定を受けることをおすすめします。
【石井建装】取手市のスレート屋根は“内部劣化の見極め”が成功の決め手|まずは専門診断を

取手市の築20〜25年のスレート屋根は、表面の割れ・反り・苔だけでは判断できない「内部の劣化」が進んでいるケースが非常に多いのが特徴です。野地板の沈み、谷板金や壁際の雨仕舞の腐食、棟板金下の貫板腐朽などは、いずれもカバー工法では改善できない根本的な欠陥です。
これらがひとつでも当てはまると、丁寧にカバーを施工してもビスが効かず、浮き・バタつき・雨漏りが再発する恐れがあります。スレート屋根は“見えている部分より内部が傷んでいる”ことが多く、施主様ご自身の目視判断では限界があるため、可否の判定には専門的な調査が不可欠です。
石井建装では、野地・貫板・雨仕舞・ルーフィングまで総合的に診断し、「カバー工法でいける屋根」と「葺き替えが必要な屋根」を写真と理由付きで明確化しています。取手市で屋根カバー工法を検討されている方は、まずは石井建装へお気軽にご相談ください。
問い合わせフォーム・メール・電話でのご相談はもちろん、ショールームへご来店いただければ、実際の施工事例や劣化サンプルを見ながら詳しくご説明いたします。
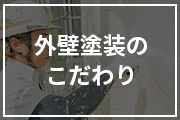
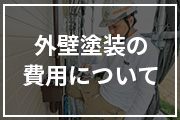
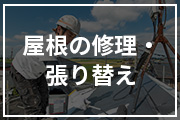
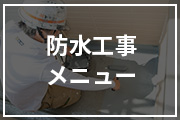

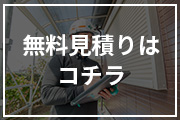

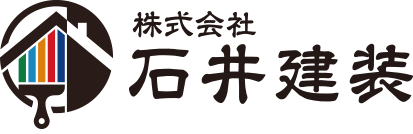











コメント