オートンイクシードの“使いこなし”|プライマー・使用m数・上塗り相性

外壁やサッシ周りの防水性を左右する「シーリング材」は、建物の寿命を左右する重要な要素です。中でもオートンイクシードは、30年耐候をうたう高耐久タイプとして、一般の住まいから公共施設まで幅広く採用されています。可塑剤を含まない独自の「LSポリマー」によって、長期にわたって柔軟性と密着性を維持できるのが特徴です。
一方で、「どんなプライマーを使うのか」「どのくらいのm数が必要なのか」「塗装との相性は?」といった具体的な施工条件を誤ると、せっかくの高耐候性能を十分に発揮できません。オートンイクシードの正しい使い方や、使用条件の理解が求められます。
そこで今回のお役立ちコラムでは、オートンイクシードについてくわしくお話しします。施工時の「温湿度条件・プライマーの選定・m数の目安・上塗り塗料の相性・施工後の養生時間」などを理解しておけば、失敗を回避できるのです。
オートンイクシードの基本性能と採用メリット

オートンイクシードは、オート化学工業株式会社開発の、長寿命シーリング材です。従来の変成シリコンと異なり、20〜30年の長期耐候性を目標に設計された耐久性を備えています。紫外線・雨水・熱劣化に強く、長期にわたって弾性を保持できるのです。新築だけではなくリフォームまで、幅広い用途で活用できます。
変成シリコンの中でも異例の長寿命設計
オートンイクシードの寿命を支えるのは、独自開発の「LSポリマー」です。一般的な可塑剤を使用せず、分子レベルで柔軟性を内包する構造となっています。このため、紫外線による硬化・ひび割れを大幅に低減し、20年以上の弾性維持が可能です。ALC・サイディング・モルタルなど、下地の動きに追従できる柔軟な対応性があります。
主成分・可とう保持剤「LSポリマー」の特性
オートンイクシードの最大の特長は、オート化学工業が独自に開発した可とう保持成分「LSポリマー」です。一般的なシーリング材は柔軟性を保つために可塑剤を含みます。そのため時間の経過とともに、可塑剤が揮発・流出すると硬化やひび割れが進行するのです。
一方、オートンイクシードは可塑剤を一切使用していません。この「LSポリマー」によって長期間にわたり柔軟性と密着性を維持できる構造が採用されています。
「LSポリマーが経年硬化による性能低下を抑制し、長期にわたって可とう性を保持する」点は大きなメリットです。外壁目地や開口部周辺の防水性能を安定的に維持できますし、再打ち替えの周期を大幅に延ばせます。
一般シーリング材との比較(耐候・硬化・可塑剤ブリード)
オートンイクシードは可塑剤を含まない設計のため、ブリード(滲み出し)や塗膜汚染のリスクがほとんどありません。また、経年での硬化や弾性低下が少ないのも特徴で、美観を長期間保ちやすいのです。
一般的な変成シリコンやウレタン系シーリングでは、紫外線や熱により硬化・収縮が進み、目地割れや密着不良を起こす場合もあります。オートンイクシードはLSポリマー構造によってその影響を抑制できるのです。長期間にわたって弾性と防水性を維持し、外壁塗装仕上げとの相性も安定しています。
参照:長期耐久型ハイクォリティーシーリング材オートンイクシード
オートンイクシードの施工条件と注意点
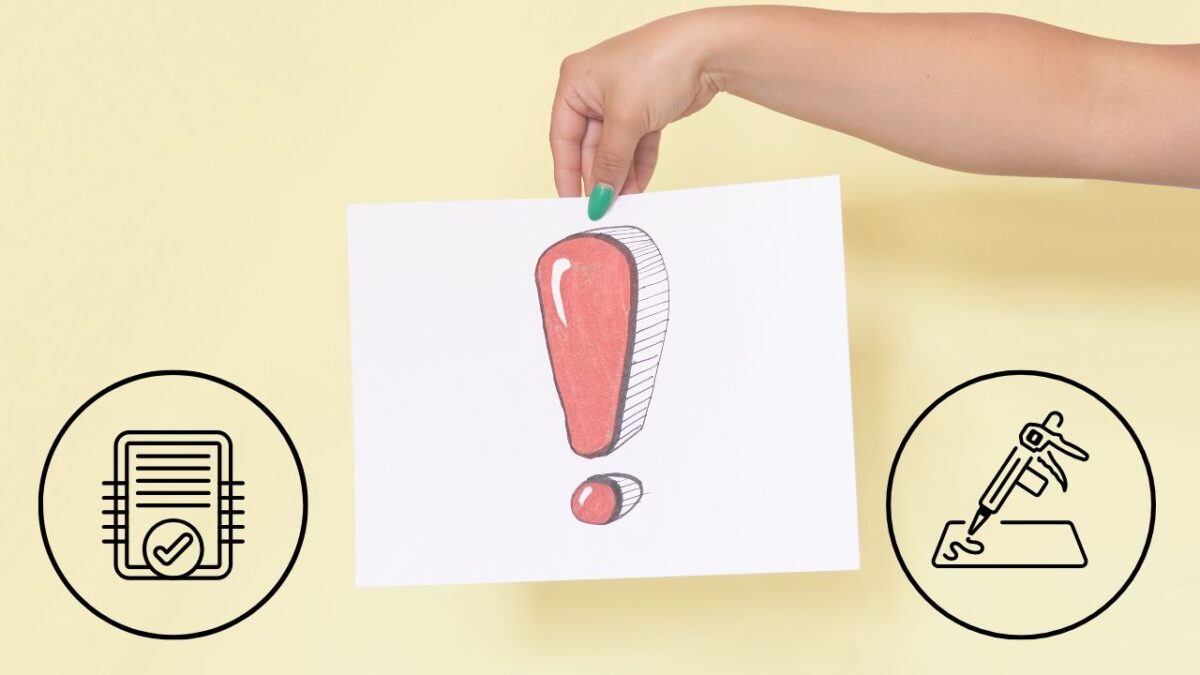
オートンイクシードは高耐候シーリング材として設計されていますが、性能を最大限に発揮するためには「正しい施工環境」と「標準手順」を厳守することが不可欠です。「温湿度」「下地処理」「プライマー塗布」「乾燥時間」など守るべきポイントをお話しします。
施工環境と事前確認
施工は晴天または曇天時に行い、気温0℃以上・湿度85%以下を条件とします。風が強く埃も舞う環境では、接着不良の原因となるため避けなければなりません。
施工直前には、下地の汚れ・油分・水分を完全に除去し、乾燥した清浄な状態を確保します。既存のシーリング材を撤去する際は、カッターやマイナスドライバーを用いて三面接着部まで確実に除去します。小口面に残存シールがあると密着不良を起こすため、必要に応じて軽く削り取ることも必要です。撤去後はブラシやエアブローで粉じんや汚れを落とし、バックアップ材を用いて二面接着構造の確保も求められます。
目地幅と深さの比率は、標準として「幅10〜20mmに対して深さ8〜20mm以内」が基本です。サイディングの凹凸や施工環境に応じて、部分的に5mmまでの浅目地も許容されています。
プライマー塗布と乾燥管理
目地清掃後、マスキングを施し、指定プライマー(OP-2019)を均一に塗布します。塗布後は15分以上(冬期30分以上)乾燥させ、充分に揮発してからシーリング材を打設する流れです。乾燥が不十分なまま打設すると、密着不良や早期剥離の原因となります。
また、プライマー塗布後に時間が経過(2時間超)した場合や、雨・結露で濡れた場合は再塗布が必要です。塗布ムラを防ぐため、刷毛は毛先を整え、施工面以外に付着しないよう、注意が必要です。
シーリング材の充填と仕上げ
打設はノズルを目地底まで差し込み、気泡を入れずに連続充填します。充填後はヘラで2回押さえを行い、初回で目地への密着を確実にし、2回目で表面を整える流れです。シーリング材の充填量が過多になると応力集中を招き、剥離や割れの原因となります。
マスキングテープは硬化前の除去が必要です。硬化後に剥がすと、表面の塗膜が引っ張られて、仕上げを損なう恐れもあります。打設後は表面に触れず、完全硬化まで、養生時間の確保が必要です。
施工上の注意点と保管条件
ここからは施工上の注意点を保管条件についてお話しします。
施工当日に開封したらその日のうちに使い切る
開封後に放置すると材料が硬化し、再使用ができません。そのため開封したら、使い切ることが前提です。また、シリコン系と変成シリコン系シーリング材を同じ日に使用は禁止されています。
アルコールや洗浄剤に注意
また、アルコール系の溶剤や洗浄剤との接触も回避が必要です。ポリウレタン系シーリング材は、アルコールと接触すると硬化不良につながります。
そのほか、火気のある場所では施工禁止です。材料は直射日光を避け、冷暗所に保管し、製造日より1年以内の使用が原則です。
施工後に上塗りを行う場合は、表面が十分硬化してから塗装します。硬化時間は気温・湿度によって異なるため、メーカーの推奨値に従って確認が必要です。
品質確保のチェックリストと見積比較ポイント
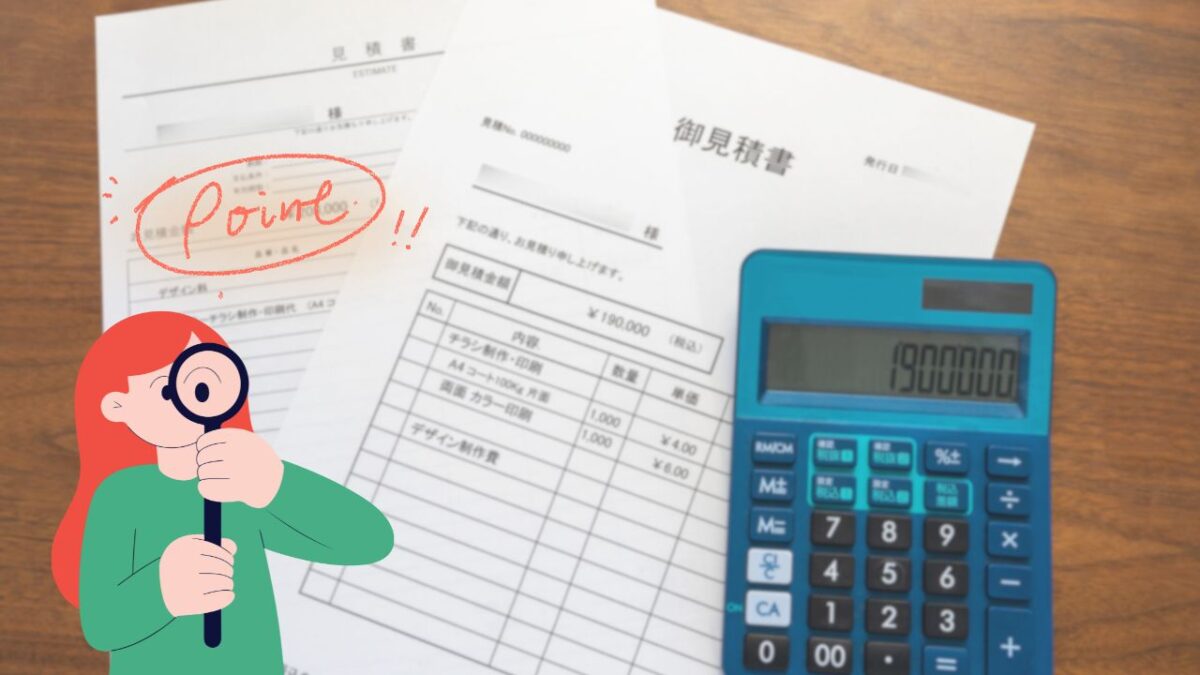
最終的な品質は、施工記録の管理と数量精度に左右されます。製品ロットや試験記録を残すことで、保証申請や再施工時の根拠資料となるのです。
現場検査で確認すべき項目(断面形状・プライマー有無)
打設後に確認すべきは、「断面形状(目地中央の厚み)」「プライマー塗布の有無」「気泡の発生」「仕上げ面の整形」です。とくにALCでは、目地中央が薄いと伸縮追従性が失われます。現場写真を記録し、1日ごとに施工報告書を残すのがポイントです。
見積書で確認すべき単価・数量・使用量
見積では、「単価(m単価)」「使用m数」「缶数」の明記を確認します。数量に乖離がある場合は要注意です。さらに、プライマー・養生・廃材処理を含むかどうかを確認することで、正確に比較できます。
保証と記録保管(製品ロット・施工報告書添付)
メーカー保証を受けるには、製品ロット・施工写真・施工日報を保管が求められます。とくに外壁改修では、完了報告時にロット番号シールを貼付しておくと、将来の保証確認が容易になるのです。
FAQ|オートンイクシードに関するよくある質問
オートンイクシードは高耐候シーリング材として多くの現場で採用されていますが、施工や管理の段階で「どのくらい持つのか」「どんな塗料と相性がいいのか」「冬場でも使えるのか」などの質問をよくいただきます。ここでは、実際の施工現場で頻出する疑問を中心に、判断や施工の参考になる内容をまとめました。
Q1:オートンイクシードの耐用年数は本当に30年ですか?
A.メーカーの促進耐候試験で約30年相当の紫外線照射に耐える性能が確認されています。これはあくまで実験室条件での加速試験結果であり、実際の環境(紫外線量、湿度、外壁素材など)によって変動します。現場では20〜25年を目安に再打ち替えを検討するケースが多く、塗り替え周期(10〜15年)と合わせて点検を行うのが理想的です。石井建装でも、10年ごとの定期診断を推奨し、劣化の兆候を早期発見できる体制を整えています。
Q2:上塗り塗料は何でも使えますか?
A.弱溶剤シリコン・ウレタン・フッ素系塗料とは高い相性を示しますが、強溶剤型は膨れ・変色・剥離のリスクがあります。オート化学工業が公開している「塗料適合表」に準拠するのが基本で、特に再塗装時は試験塗り(パッチテスト)を行うのが確実です。石井建装では塗料メーカーと連携し、使用環境・既存塗膜の種類を踏まえた適合確認を行っています。これにより、塗膜汚染や可塑剤ブリードの心配を最小限に抑えることが可能です。
Q3:表面硬化時間は安定していますか?
A.季節や気象条件により硬化速度は大きく変わります。春・秋は約24時間で表面硬化しますが、冬季(5℃前後)では2〜3日かかることもあります。湿度が高いと揮発が遅れ、気泡や剥離の原因になるため、気温5℃未満・湿度85%以上では施工を避けるのが基本です。石井建装では、毎日の温湿度を施工日報に記録し、硬化管理や保証対応時の根拠資料として保存しています。
Q4:増し打ちはできますか?
A.完全撤去が難しい箇所(特にサッシ周り)では、増し打ちによる改修も可能です。ただし、増し打ちは既存シーリング材の劣化状態に影響されやすく、メーカー保証の対象外になる場合があります。そのため、目地内の旧シーリングが粉化・剥離していないか確認したうえで、プライマーの再塗布と表面処理を行う必要があります。石井建装では、撤去・増し打ちの可否を現場で判断し、保証範囲とリスクを明示した上で提案しています。
オートンイクシードの施工相談は石井建装へ|最適プライマー選定とm数算定まで一括サポート

オートンイクシードの性能を引き出す鍵は、現場の温湿度管理、二面接着の確保、適切なプライマー選定、目地幅×深さに基づくm数と使用量の正確な算定、そして上塗り塗料の相性確認です。
石井建装では、下地診断からOP系プライマーの塗布条件管理、打設後の断面形状・気泡有無の検査、ロット番号や施工写真の記録保管までを標準化し、長期耐久を前提とした改修品質を担保します。
サイディング目地やサッシ周りの撤去可否判断、増し打ち可否のリスク説明、硬化所要時間の季節補正、塗装前の養生時間管理なども職人が数値で説明するため、仕上がりと保証の根拠が明確です。プライマーの再塗布要否や強溶剤との相性チェック、缶数とm単価の整合など、見積比較で迷いやすいポイントも実務ベースで解消します。
オートンイクシードでの改修を確実に成功させたい方は、お問い合わせフォーム・メール・電話・ショールーム来店のいずれからでも石井建装へご相談ください。
現場条件に最適化した仕様書づくりと数量精査で、無駄のない費用と長持ちする防水性能をご提供します。
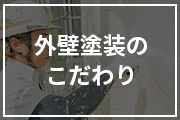
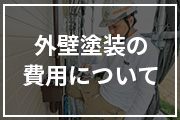
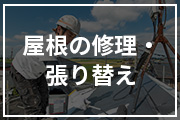
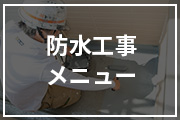

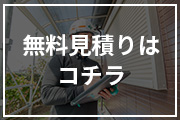

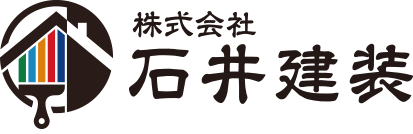






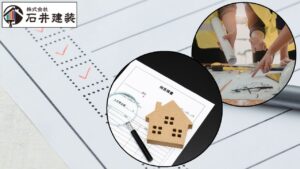




コメント